















第二十一章
起きてしまったことは仕方がない。何をするかも問題ではない。生きてくのが問題なのだ。
「なあ、こっちこいよ」
カノコをつつくタケオ。スーパーDJで日々レコード屋でLPをあさる毎日だ。
ディスクユニオン、ハッピーデイズカモン。店員と友達になるのさ。
「とはいえ、なんとはいえ、なんつーかさあ、おまえ変だよ」
タケオの、それでいて不思議な目に映るカノコの見上げる生意気でいて、かつ、くるしゅうない姿にぞっこんなタケオだ。いやいや、のろけかな。
「あたしってハイパーマルチメディアな書籍なの。生きていくってなんなのか、いっつも考えてなきゃならないでしょ。それなのに答えはいっつも未来にあって、どんどん先送り。未来なのにいつまでたっても実現されない。悲しい性なのかしら」
悲しいなんてこれっぽっちも思っていないのに思ってるふり。悲しいふり。これこそ文化!ああ、なんてすばらしきタンパク質の浪費なのかしら・・。
首をかしげるカノコにタカオは机の端にある落ちそうなたぷたぷオレンジジュースを手にとって、ずずずとすする。表面張力のおかげなの。ウヒョ。
「オレンジすすってんじゃないわよ。オレンジはね、生きながらにして生き血、生き血よ?分かってる?吸われてるのよ、献血、なんて生易しいものじゃないの。そりゃやってることはさ、見た目が整備されてシステム化されてるだけでおんなじなんだけどさ」
「・・・で、そのなんだっけ、その献血と違って、なんというかさ、足元みたら自分の足をワニに食われてた!みたいなのとおんなじなの。世界残酷ももんが物語ね。その残酷に荷担してるのがあなた。少しは認識するところからはじめなさいよ。ちょっとね、暗い部屋で塩化ビニール廻してるからっていい気にならないの。所詮、悪魔なんだから。悪魔っていっても子悪魔だけど(うわ、ダッサー)」
珍しく他人にかまうカノコ。銅のドラゴンピアスがタケオの耳で黒光りする。火を吹くってウワサ、本当なのかな、と指でつついて恋人づらするところに、母親がゲッチュウ。
「まあたべたべたしくさりおってからに!台所手伝いなさい!」
母親は、「はあ〜い」と声の音速よりも早くだんだんだんと階段を降りて庭の物置のジャガイモを検索。カノコ、台所で皿洗いに接続。ドラゴン黒光りなタケオは転がっている女子高生写真投稿誌をぺらぺらし、「おれ、クラブ行くわ」と玄関で靴を履きーの。
「壊れないことが大事なの。でもどんなものも絶対壊れるから、壊れないことが愛だって信じちゃだめなのよ。お皿って壊れるけど、でも、まず、壊れないでしょ。それは運ぶ人の愛があるから。そして出来るまでに超高温で鍛練されてるからなの。包丁も一緒。」
すらりと立った体をひねり、ジャキン!と包丁をすっくと構えるカノコ。遠く玄関でビビるタケオ。(「おれまだ別れねーよー」)
「あつーくしてカンカンして、ジューって冷やして、またあつーくして。愛なの。とろけさせて、冷まして、そして鍛える。冷える瞬間に人間としての価値が決まるのよ。熱いときはだめなの。固まるときが大事。いつ固まるか、いつ冷やされるのか、人が横をとおっても気がつかないくらいすずめに集中しているノラネコのように瞬間を待つの。でも待っちゃダメ。スタンバイにしておいて、あつーくとろとろに身を任せるの。わかる?こころの奥底に起爆スイッチをおいたら、あとは放っておくの。」
しゃべりすぎて処理の低下。皿は山のよう。母親は間でジャガイモを剥きはじめる。皿洗いの中に、人生を見出そうとしているのか、水の流れにふと手をかざし、考える。窓の外の、姿は見えないけれど確実にあるだろう三日月のその姿に、愛を見い出そう。ハッピーラブトゥデイ。君のために。

|
|
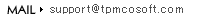 までどうぞ。go toトップページ
までどうぞ。go toトップページ
